Science/Research 詳細
3Dプリンタを活用した安価な材料合成ロボットの開発
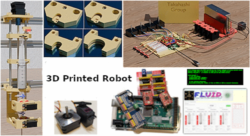
May, 8, 2025, 札幌--北海道大学 大学院理学研究院・総合イノベーション創発機構 化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)の髙橋 啓介 教授、髙橋 ローレン 助教、クワハラ・ミカエル 学術研究員、前田理教授らの研究グループは、3Dプリンタを活用して完全自作可能な材料合成ロボット「FLUID」を開発した。
これまで、研究グループは触媒インフォマティクスを活用し、人工知能による材料開発を実現してきた。しかし、触媒の合成や評価は依然として人が担っており、化学実験の完全自動化には至っていなかった。一方、海外では化学合成ロボットの販売が始まっているが、高額かつ汎用性の低さが導入の大きな障壁となっていた。
研究グループは、安価で誰もが手に入れられる汎用部品のみで構築できる材料合成ロボットの開発に取り組んだ。大部分の部品を3Dプリンタでプリントし、ネジやモータなど、特別な部品を使わずに組み立てられる設計を実現した。汎用部品のみで構成する場合、精密な動作制御が技術的な課題だっが、独自の機構設計と独自の制御ソフトウェアを開発することで、低コストながら高精度な操作を可能にした。そのため、従来の高価なロボットと同等の機能を持ちながら、手軽に導入できる革新的な材料合成ロボットを開発することができた。
今回開発したロボットを正確に制御する独自のソフトウェアは、直感的なインタフェースを備えており、専門知識がなくても簡単に操作できる点も特徴である。より多くの研究者や技術者がロボットを活用し、新しい材料の開発に貢献できることが期待される。
開発されたロボットの最大の特徴は、その完全オープンソース化である。設計図や電気回路図、組み込みシステム、組み立て方法、3Dプリンタデザインファイル、ロボット制御ソフトウェアのソースコード、使用した部品のリストなどをすべて公開した。産業界や研究機関のみならず、誰でも自由に利用・改良できる環境を整えた。さらに、開発したロボット「FLUID」を用いて、実際に材料合成を実施した。その結果、材料ロボットによる共沈法を実施し、ニッケルとコバルトの酸化物を人の手を使わずに合成することに成功した。研究では、ロボットを正確に制御する独自のソフトウェアを開発し、溶液の供給速度や混合プロセスを綿密に調整できるようにした。これにより、従来の高価な装置でも難しかった流体制御を実現し、均一な粒子サイズや組成を持つ酸化物の合成が可能となった。この精密な流体制御技術は、より複雑な材料合成や化学反応開発にも応用できると期待される。
また、ロボットの設計データや制御ソフトウェアは、GitHub(https://github.com/Materials-Informatics-Group)でGPL3.0ライセンスのもと、誰でも無償でアクセス可能。この成果は、低コストで自由度の高い材料合成ロボットの実現可能性を示すものであり、今後の材料開発の自動化の発展に大きく貢献すると期待される。
研究成果は、日本時間2025年4月9日(水)に、米国化学会「ACS Applied Engineering Materials」誌にてオンライン公開された。
研究成果は、2025年4月9日(水)に、米国化学会(ACS Applied Engineering Materials)誌にてオンライン公開された。また、ロボットの設計データや制御ソフトウェアは、GitHub(https://github.com/Materials-Informatics-Group)でGPL3.0ライセンスのもと、だれでも無償でアクセス可能である。この成果は、低コストで自由度の高い材料合成ロボットの実現可能性を示すものであり、今後の材料開発の自動化の発展に大きく貢献すると期待される。
論文名:Development of an Open-Source 3D-Printed Material Synthesis Robot FLUID: Hardware and Software Blueprints for Accessible Automation in Materials Science(3D2プリンタによる材料合成ロボット「FLUID」の開発)
URL:https://doi.org/10.1021/acsaenm.5c00084



